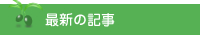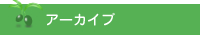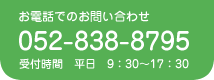
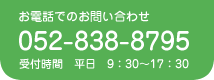

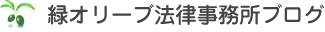

妊娠中の女性が自動車にはねられて、女性は死亡した、他方、お腹の子は死亡せず、事故後に生まれたものの重い障害が残った、という事件について、死亡した女性に対する過失運転致死罪の刑事裁判が始まりました。この裁判では、事故当時は胎児だった子に対する罪が問われていないため、ご家族が子も被害者として認めるよう検察に求めています。ネット署名で多数の署名が集まり、大きく報道もされています。(NHK NEWS WEB・9月2日等)
「胎児性傷害」:「胎児の段階で故意または過失によって傷害を負わせ、その傷害が出生後にも影響を及ぼした場合に、行為者に何罪が成立するか?」という問題が、古くから議論されてきました。
日本の刑法において、胎児は「堕胎の罪」によって保護されています。「堕胎」とは「自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離させること」と定義されていますので、胎児に何かしらの傷害を負わせたからといって、「堕胎」の罪に問われるとは限りません。
そこで、胎児に対する傷害罪・過失傷害罪の成否が問題となります。ところが、日本の刑法において、胎児は母親の体の外に出てはじめて「人」と認められるとされていていますので、事故当時は「人」ではないことになってしまいます。
これが「胎児性傷害」の問題です。
以下、私が司法試験の受験生時代に勉強したことをまとめます。
【否定説】
胎児は「人」でない以上、過失傷害罪等は成立しないという見解
【肯定説】
① 生まれてきた「子」(=「人」であるY)に対する傷害を認める見解
② 身ごもっていた「母」(=「人」であるX)に対する傷害を認める見解
a 胎児を「母体の一部」とみる見解
b 母体の「健康な子を出産する機能」を害するとみる見解
実は、否定説が、学説上の通説です。
現行法の解釈としては、「人」に対する罪の成立を認めることはできない、胎児性傷害の可罰化は、立法的解決によるほかない、といいます。処罰という国家による制裁を伴うのだから、あらかじめ議会が民主的に定める成文の法律をもって規定しておかなければならない、という大原則に忠実な見解だといえます。
しかし、これでは硬直的で冷淡だとして、肯定説が主張されます。
有名な熊本水俣病の刑事事件で、第一審熊本地裁は、肯定説①を採用しました。
胎児と「人」は価値的には差がなく、傷害の結果が発生した時点で客体である「人」が存在すればよい、として、生まれてきた子Yに対する過失傷害罪が成立するとします。
他方、同事件の最高裁は、肯定説②-aを採用しました。
現行法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと取り扱われていると解されるから、過失傷害罪の成否を論ずるにあたっては、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない、とします。
肯定説②-bは、母体の「健康な子どもを出産する機能」が害されたとして、母親Xに対する過失傷害罪が成立する、とします。
個人的には、罪刑法定主義という大原則には忠実であるべきで、立法的解決が望ましいと考えていますが(否定説)、ご家族の気持ちはもっともなことです。
今回の事件では、検察官が子の怪我の状況の補充捜査を申し出たとのことで、子も被害者とするか再検討されるかもしれません。推移を見守りたいと思います。(浜島将周)
<9.5.追記>
ひとつ質問を頂いたので、追記しておきます。
胎児の民事上の地位については、民法721条に、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」という規定があります。したがって、胎児が無事に生まれたときは、交通事故の加害者に対し、子固有の損害賠償請求をできます(実際には、その子の保護者が、法定代理人として請求することになるでしょう。)。
他方、流産などで実際に生まれなかったときは、子固有の損害賠償請求はできません。
― 緑オリーブ法律事務所は名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にみなさまの身近なトラブル解決をサポートする弁護士の事務所です ―