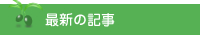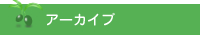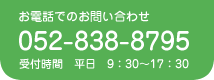
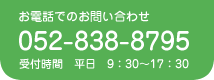

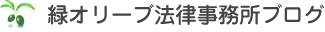

先日、交通事故死の障害児の逸失利益について、労働者の平均賃金そのままとして減額しないとした判決がありました。(NHK NEWS WEB・1月20日、産経新聞WEB・1月20日)
以前、当ブログにおいて、障害者についても、「賃金センサスの一定割合により逸失利益を算定する裁判例が増えてきています。今後、…障害者をめぐる法整備や雇用状況の改善がさらに進めば、賃金センサスそのものを基準とした逸失利益の算定をする判断も出てくるでしょうし、そういう社会であるべきだと思います。」とご紹介しましたが(当ブログ2021.9.13.「障害者の逸失利益」 「逸失利益」についての基本的な考え方などはこちらをご覧ください。)、まさにそういう判断が示されました。
本件は、当時11歳の女児が死亡した交通事故について、遺族であるご両親が運転手と勤務先会社を相手方にして損害賠償請求訴訟を提起したもので、裁判では、女児が将来得られるはずだった収入(逸失利益)をどう算定するかが大きな争点になりました。
第一審・大阪地裁は、障害者雇用実態調査(平成30年)における聴覚障害者の平均収入が、同年の全労働者平均賃金の約7割であることに言及しつつも、女児の個別事情や障害者の労働環境の変化をふまえて、賃金センサスの全労働者賃金平均の85%を基礎収入として逸失利益を算定しました。
これに対し、控訴審・大阪高裁は、まず、未成年者の逸失利益の認定にあたって、「全労働者の平均賃金から減額することが許容されるのは、平均賃金を基礎収入として認めることについて、顕著な妨げとなる理由がある場合に限られる」という基本的な考え方を示しました。
そして、女児が学年相応の言語力と学力を身に付けていたと認定した上で、さらに現在の就労環境について、デジタル化を中核とする技術の進歩も相まって、聴覚障害者にとって社会的障壁となりうる障害も、「ささやかな合理的配慮」によって職場全体で取り除くことができるようになっている」と指摘しました。
結論として、女児が健常者と同じ職場で、同じ勤務条件や労働環境で、同等に働くことが十分可能だったとして、全労働者の平均賃金から減額せずに逸失利益を算定すべきだとして、100%を基礎収入として逸失利益を算定しました。
障害がある未成年者を巡り、全労働者賃金平均と同等の逸失利益を認めた判決は初めてとみられます。「ささやかな合理的配慮」によって障壁は取り除かれ、障害があっても同じ職場、同じ条件で働けるのだという今回の判断は、社会の変化や実態に向き合った、評価されるべき判決だと思います。(浜島将周)
― 緑オリーブ法律事務所は名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にみなさまの身近なトラブル解決をサポートする弁護士の事務所です ―